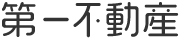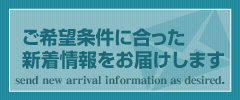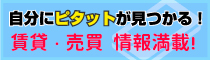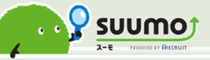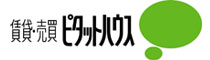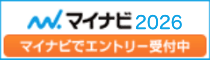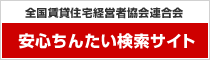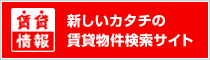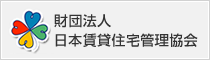STAFF COLUMN 中田 礼彦のコラム
新耐震基準
日本の建築物の耐震基準は、関東大震災(1923年)、福井地震(48年)、十勝沖地震 (68年)、宮城県沖地震(78年)といった大地震が発生するたび、新基準の制定や改正が繰り返されてきましたが、なかでも特に重要なのは、1981年の建築基準法大改正です。
78年の宮城県沖地震は、死者28人という人的被害もさることながら、建物の全半壊も7400戸に及び、耐震性強化の必要性が改めてクローズアップされました。
これを教訓に改正法は、住宅やマンション、ビルなどの建築物を「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7割り程度の大規模地震でも倒壊は免れる」強さとすることを義務づけ、新たな設計基準を設けました。これが現在も使われている「新耐震基準」です。
この新耐震基準の有効性は、はからずも阪神大震災において証明されています。
震災後の神戸市の調査では、81年以降に建てられた建物の約80%が軽微な被害(もしくは全く
被害なし)に止まり、大破・倒壊した建物はわずか1%。逆に80年以前の「旧耐震基準」 の建物は、約80%がなんらかの被害を受けており、大破・倒壊などの甚大な被害を受けた建物も相当数に上っています。
ところが、このような旧耐震基準の建物が、日本にはまだ数多く存在しています。
例えば住宅(マンション含む)の場合、98年の「住宅・土地統計調査」で約5割、03年の同調査では約4割が80年以前の建物ですから、現在でも少なくとも約3割ほどは旧耐震基準の建物ではないかと考えられます
78年の宮城県沖地震は、死者28人という人的被害もさることながら、建物の全半壊も7400戸に及び、耐震性強化の必要性が改めてクローズアップされました。
これを教訓に改正法は、住宅やマンション、ビルなどの建築物を「震度5強程度の中規模地震では軽微な損傷、震度6強から7割り程度の大規模地震でも倒壊は免れる」強さとすることを義務づけ、新たな設計基準を設けました。これが現在も使われている「新耐震基準」です。
この新耐震基準の有効性は、はからずも阪神大震災において証明されています。
震災後の神戸市の調査では、81年以降に建てられた建物の約80%が軽微な被害(もしくは全く
被害なし)に止まり、大破・倒壊した建物はわずか1%。逆に80年以前の「旧耐震基準」 の建物は、約80%がなんらかの被害を受けており、大破・倒壊などの甚大な被害を受けた建物も相当数に上っています。
ところが、このような旧耐震基準の建物が、日本にはまだ数多く存在しています。
例えば住宅(マンション含む)の場合、98年の「住宅・土地統計調査」で約5割、03年の同調査では約4割が80年以前の建物ですから、現在でも少なくとも約3割ほどは旧耐震基準の建物ではないかと考えられます