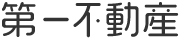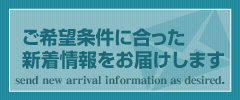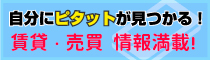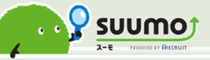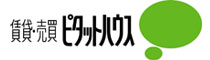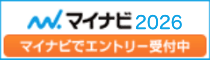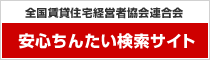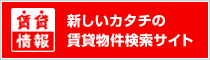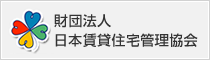STAFF COLUMN 中田 礼彦のコラム
今後の高齢化住宅について
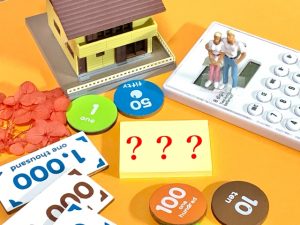
2022年の段階で、日本の人口1億2471万人のうち65歳以上の高齢者は3627万人で総人口29.1%を占めており、2040年には35.3%に達すると予想されているそうです。それに伴って、高齢者の単身世帯数も2020年には703万世帯であったのが、2040年には896万世帯に増加すると予想されているとの事です。前述に述べた様に今後の日本は否応なく高齢化社会に突入していく状況にありますが、その中で高齢者の単身世帯の31%が公営住宅や民間の賃貸住宅に居住していることから、今後は高齢者の民間賃貸住宅の需要がますます増加すると予想されているのです。
しかし、高齢者用の民間賃貸住宅については、本当にそれだけの需要を吸収できるだけの供給が確保されるのかが不安な状況にあるようです。これまで若者向けに建てられていた賃貸住宅を高齢者に提供すればよいという単純な問題ではなく、高齢者に対する賃貸住宅の提供については法律的な障害を解決しない限り促進を期待できない点があるからです。障害の一つとして挙げられるのが賃借権の相続の問題です。賃借権は財産権として相続の対象となるので高齢者が賃借後に死亡したときに賃借権が相続されることにより、解約などの処理をすることが難しくなるという問題が発生します。そのため、今後の高齢化社会においては、賃借権の相続により発生する問題を事前に解決するための法律的な手段として死後事務委任を活用することがますます重要になってくるのではないかと思います。